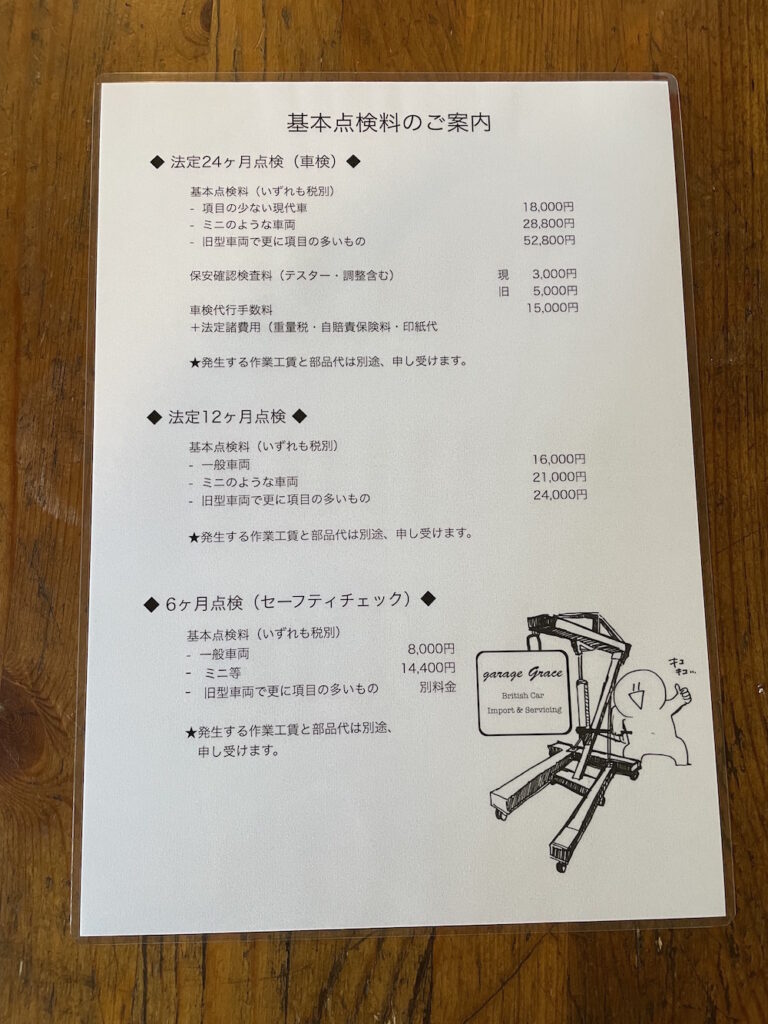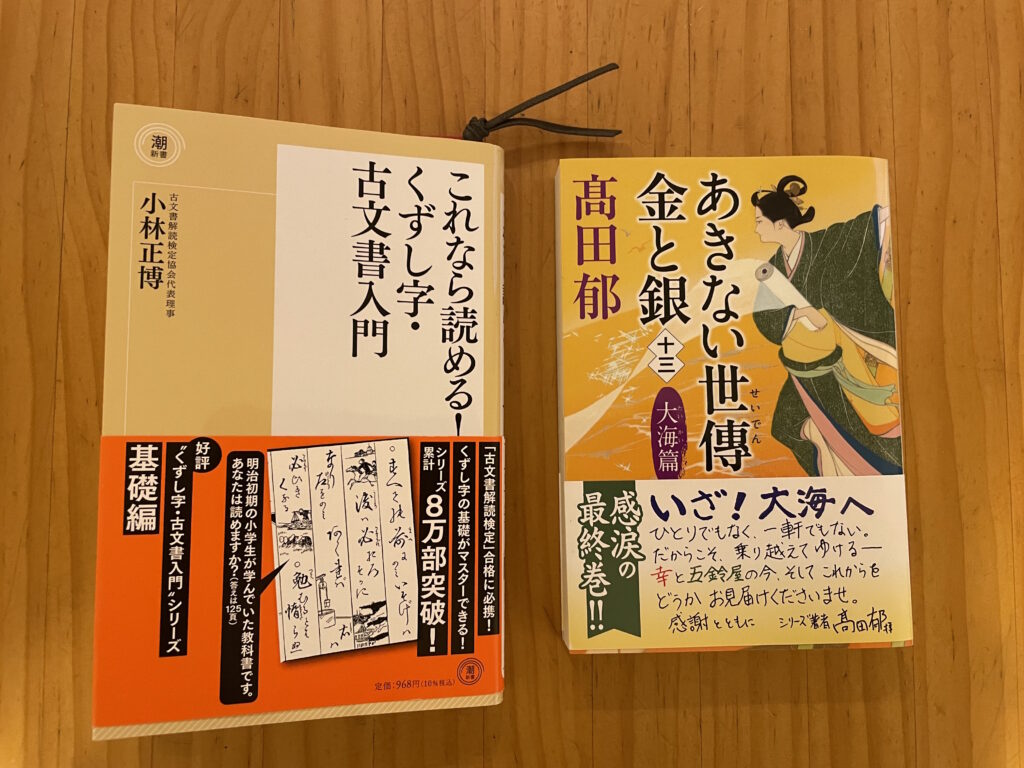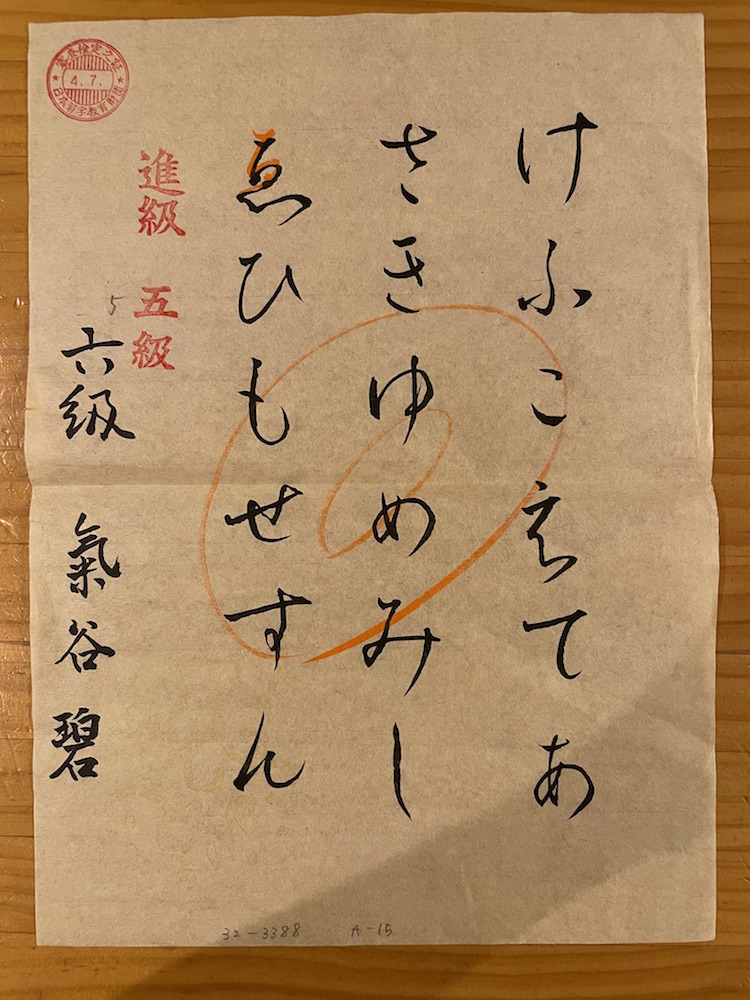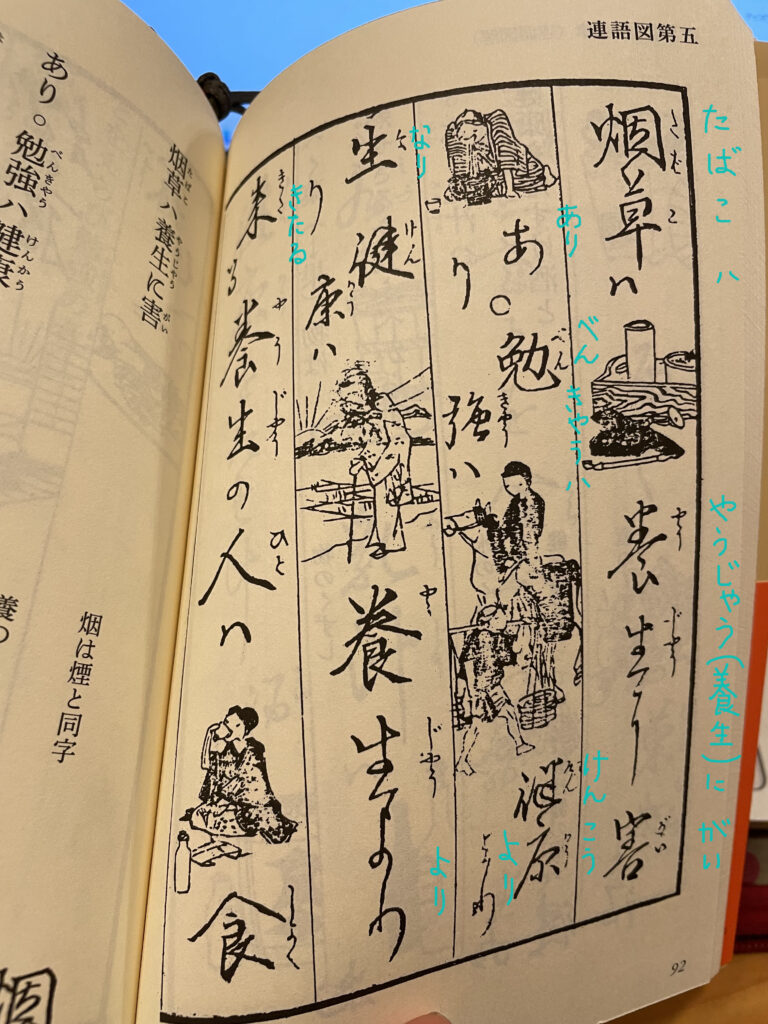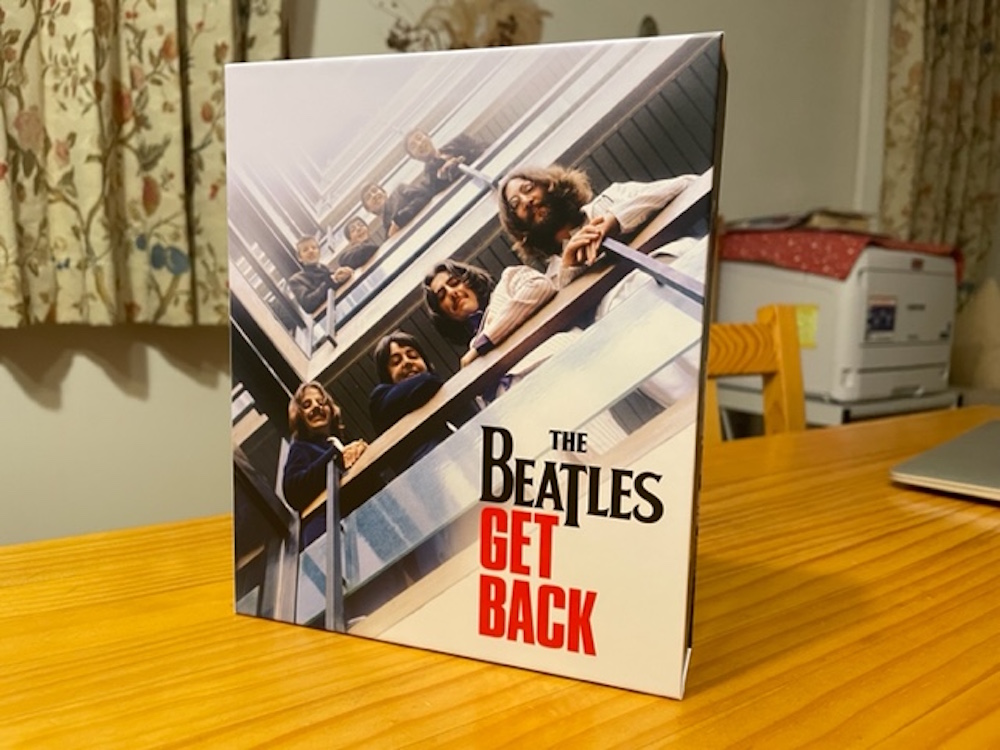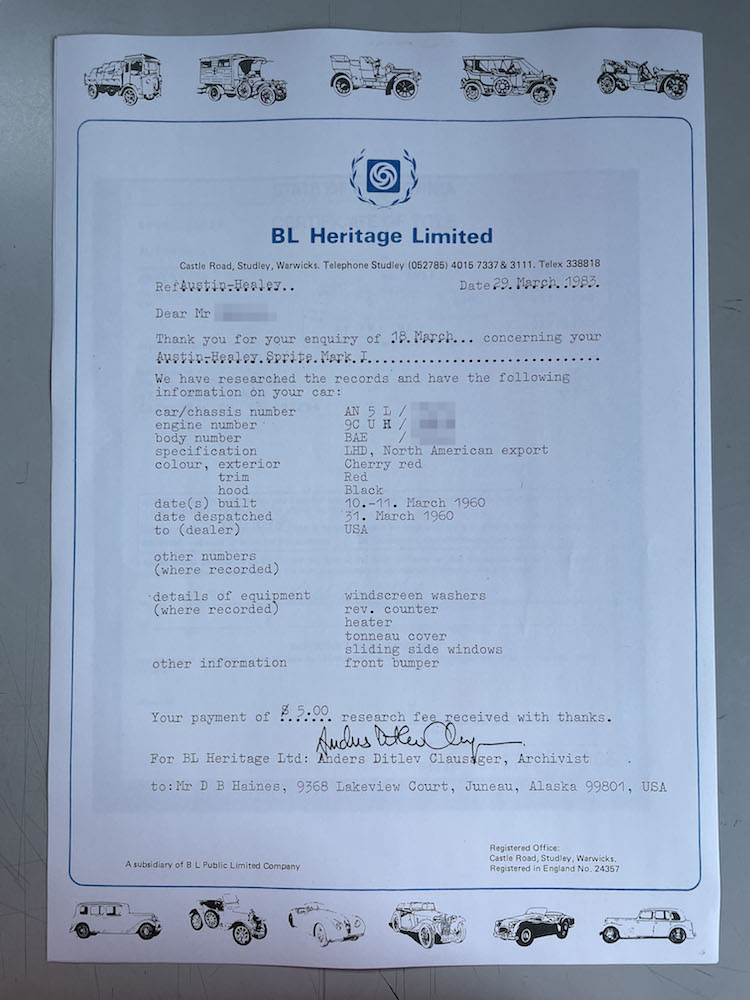今年渡英した時に、現地パートナー Paul が使ってたタイバンド。
積載車の上で車両を留める道具なんですが、タイヤに噛ませて留めるタイプ。
ボディから引っ掛けるより、負担が少ないし転がる元を抑えるから効率もいい!
コレです!

拡大!

日本じゃ売ってません。
ってことで、向こうから買いました。

トラックの荷台、要加工ですが車両の負荷が減らせます…楽しみ。
***
トーゲージ。
トー角を測る道具で、ラリーやレースで遠征の時には持って出かけます。
デジタルのものを見つけました。
どうやらここ数年で開発された商品みたいです…従来品とは比べ物にならないコンパクトさ!こんな箱に収まっちゃう。

ナニナニ…自宅で自分で正確に測れるので、専門家に出す手間や要する時間、コストが節約できる、
ウムウム…
これは取扱説明書をきちんと和訳して、それこそ手軽に苦なく使えるようにしておく必要がありそう。
やるか…