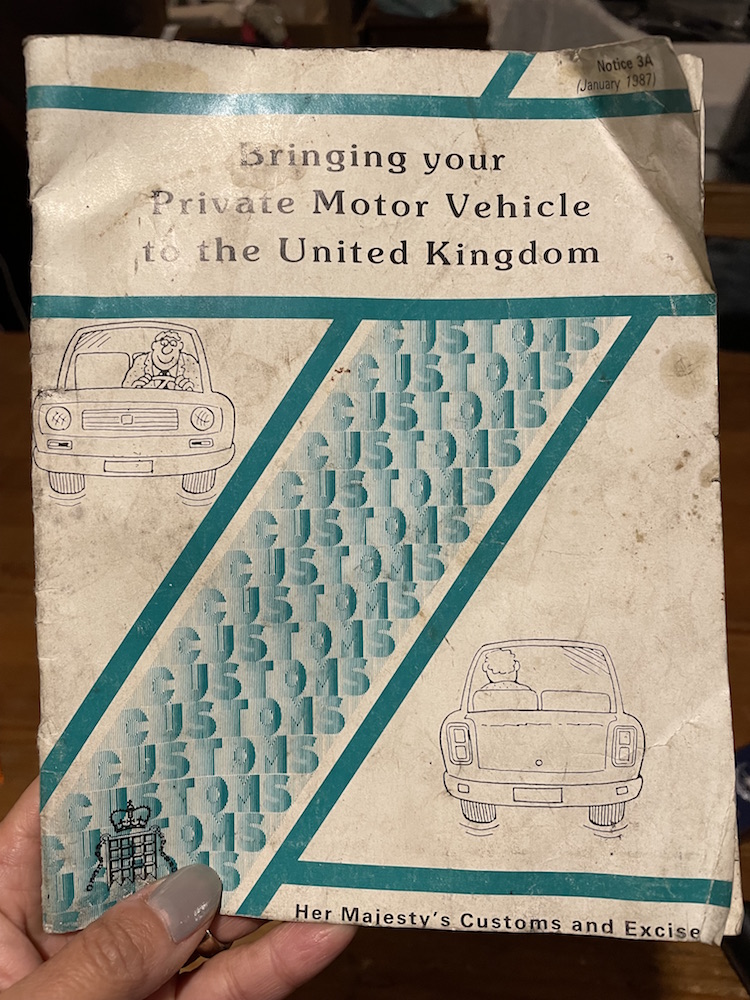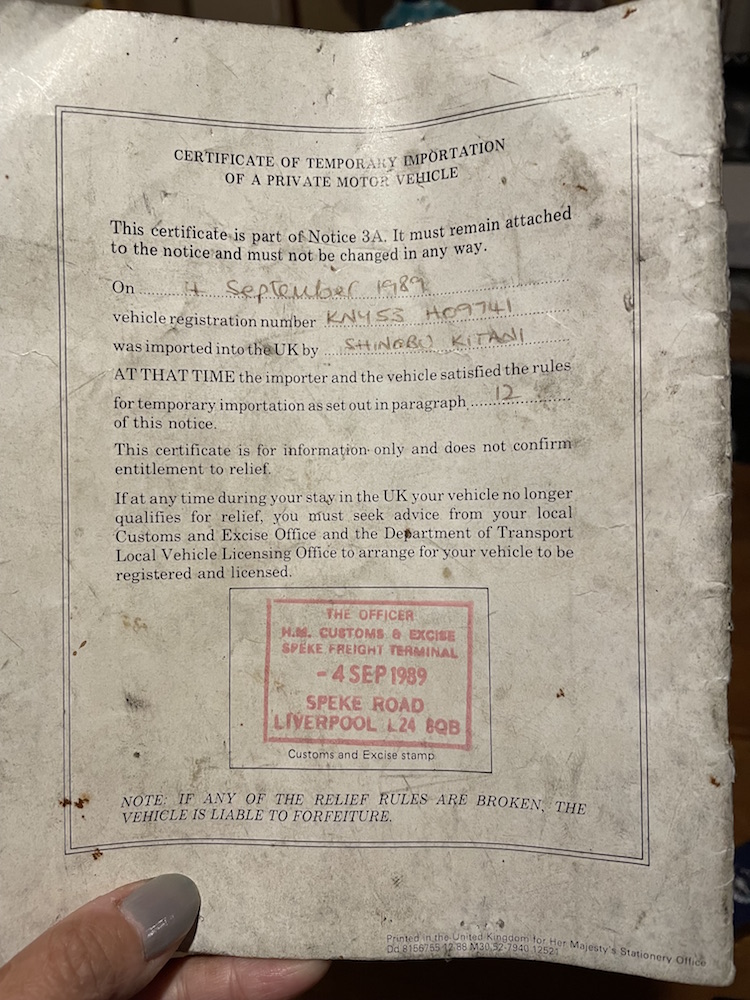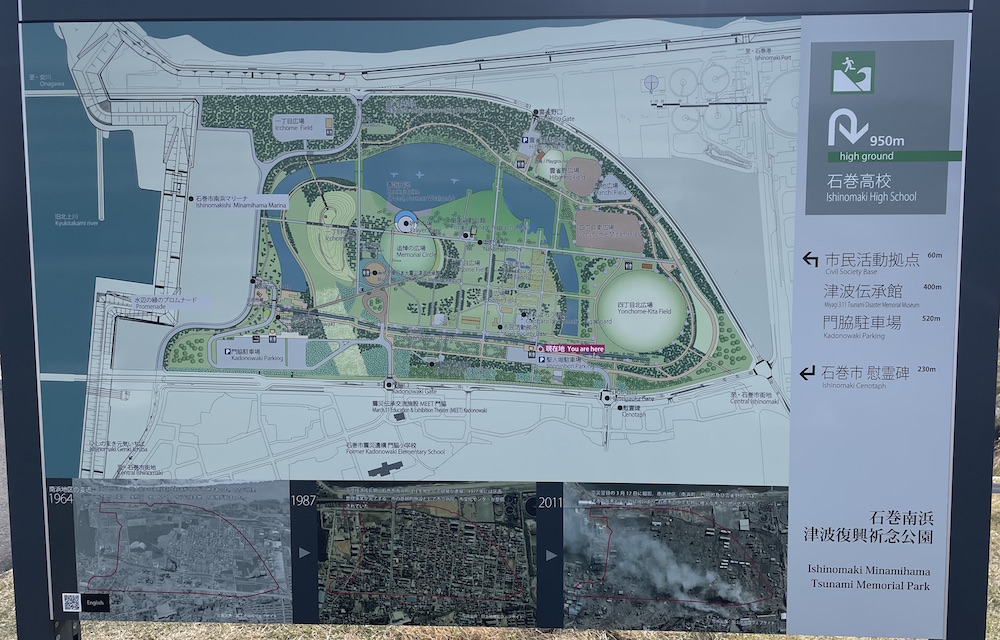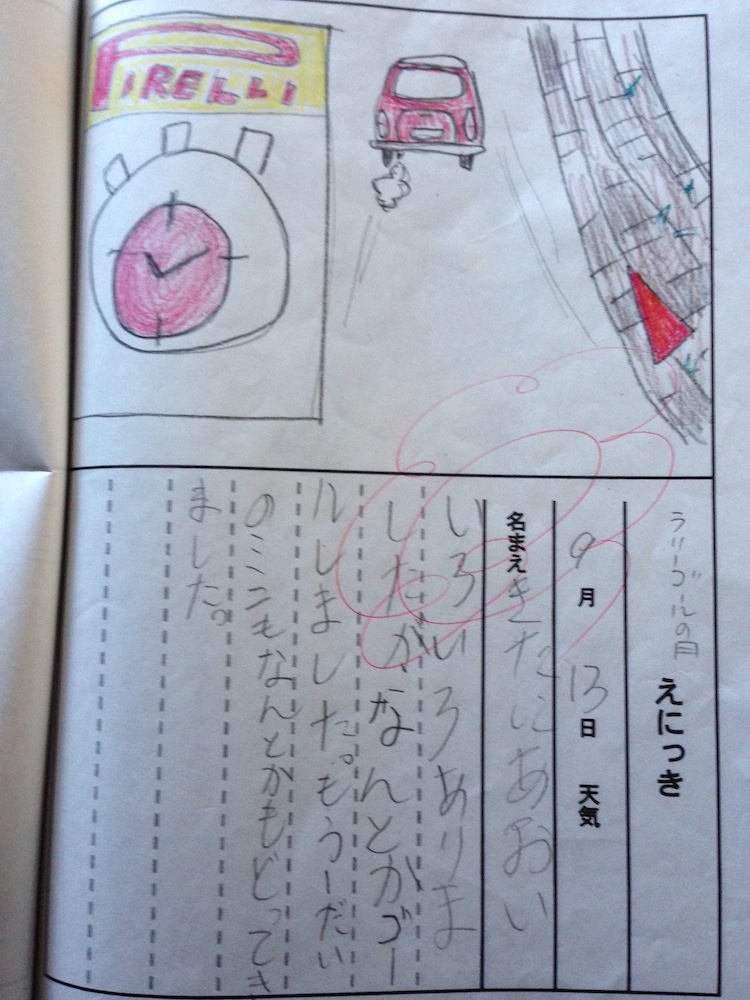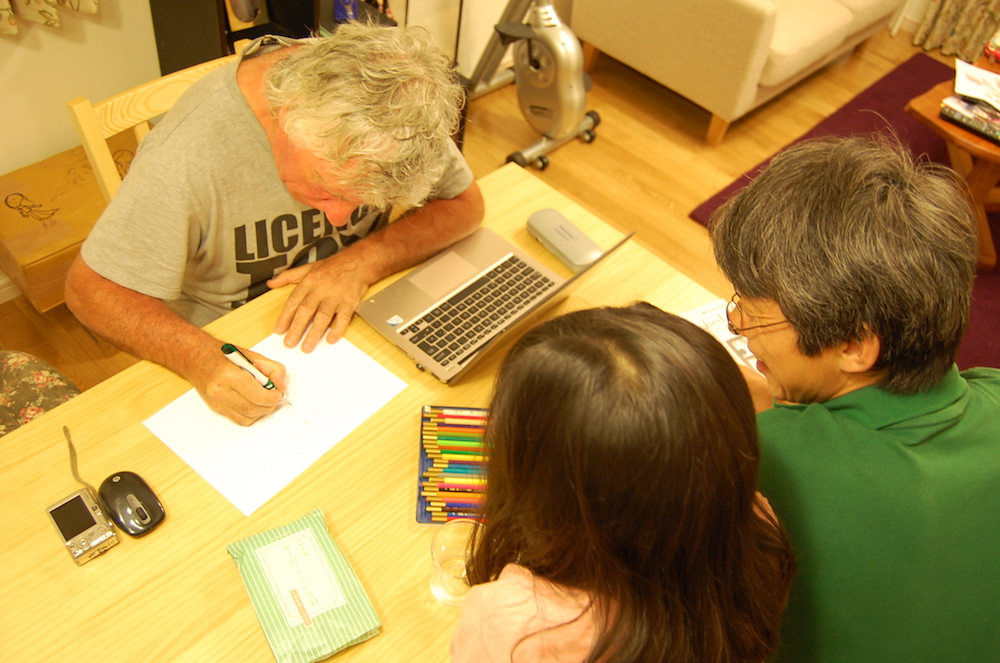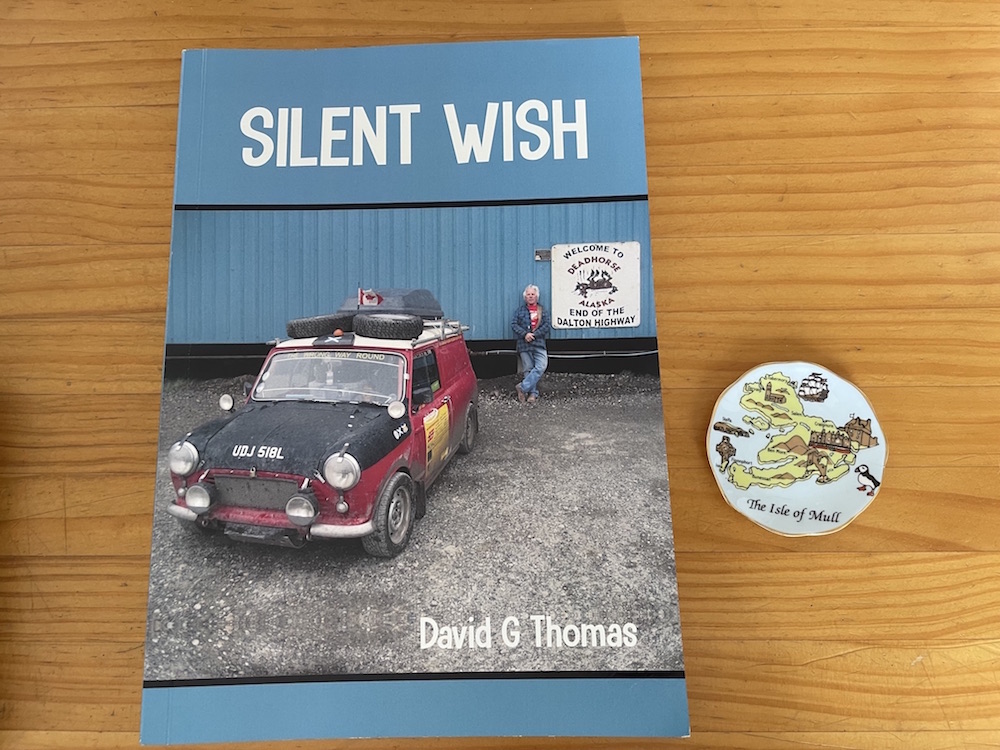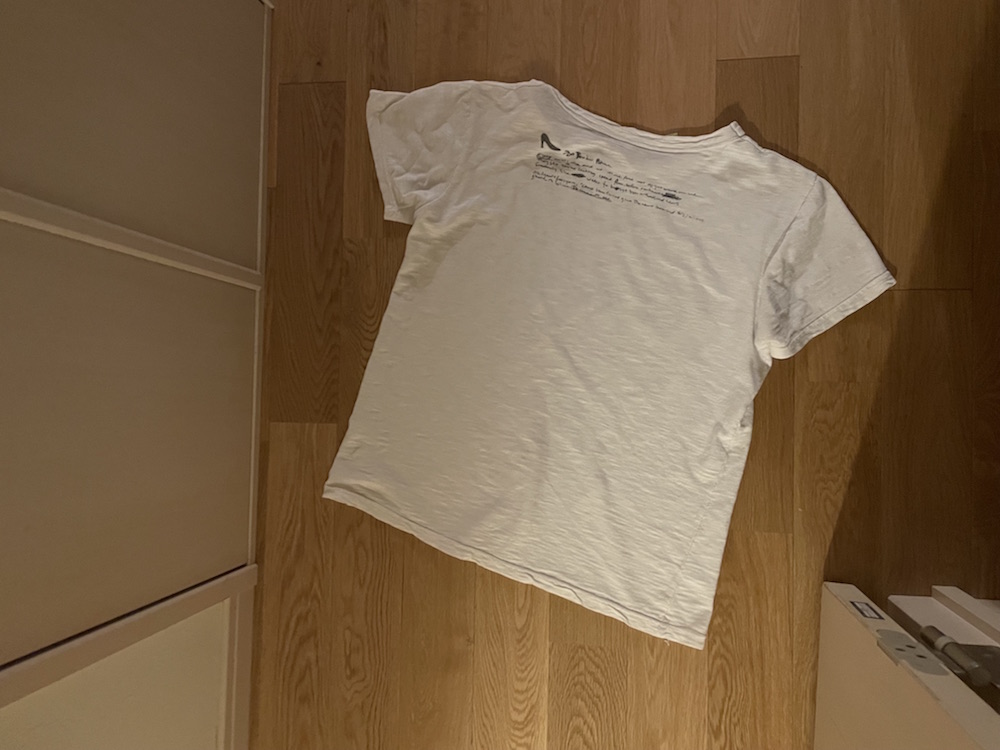ディストリビューターをリペアに出したのは、1月20日のことでした。
先方に到着後、すぐ連絡がありました。
無事受け取ったよ!最優先でやるから待ってて!
そして今日、もう帰ってきた!
仕事、速〜い ❤︎
おっ送り状が進化してるぞ…
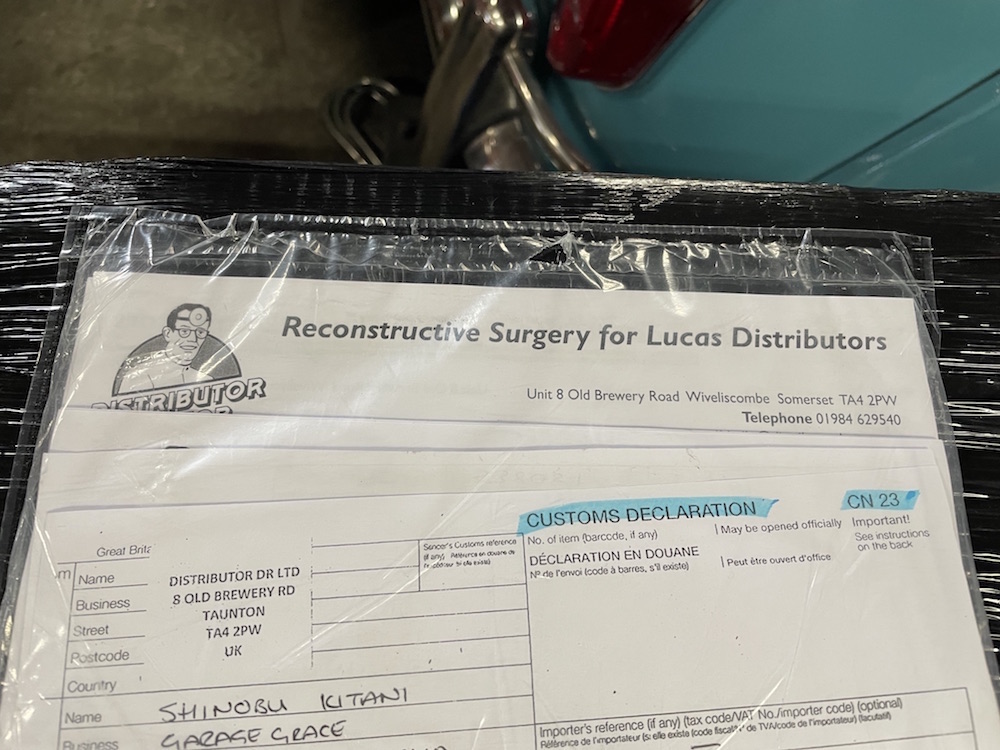
“Reconstructive Surgery for Lucas Distributors”
(ルーカス製ディストリビューターの修復手術)
彼の技術のおかげで、我々の車は元気に走り続けることができます。
しかも、速いだけでなく丁寧。
彼の仕事、超好みです。
お…なんか彼の仕事を表すワンポイントが付くようになったぞ…
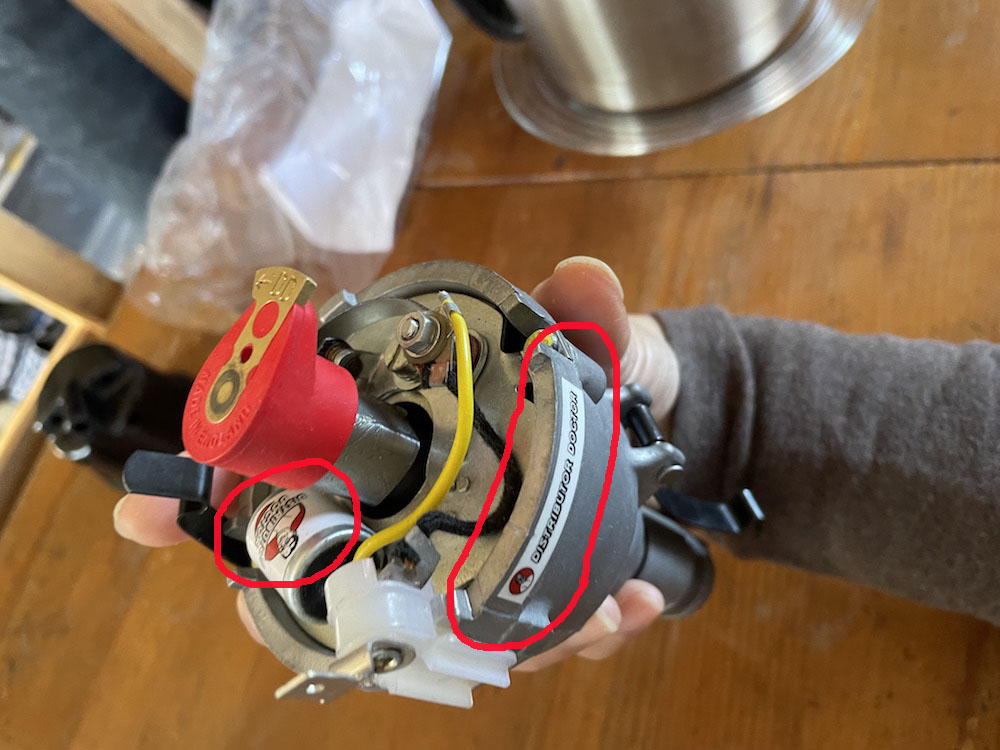
彼の自信の表れ。
そして需要があって彼の技術を頼る人はたくさん。
我々もその恩恵に預かっています。
—

これは2014年4月に単身、数日だけ仕事で渡英した時。
この時初めて、Doctor を訪れました。
特に大きな看板が出ているわけでもなく、出ているのはコレだけ。
女房殿に詳細地図をもらい、OS の地図とを頼りに向かったのですが、同じ道を行ったり来たり。
諦めかけた時、思い出したのが
「ゴミ箱のあるところ、人の営みあり」
写真には写っていませんが、杭のたもとに横に倒したゴミ箱が。
レンタカーを停めてよーく見たら、Doctor がにっこり笑ってた…
あれから10年も経つのかぁ。
程なくして Doctor は工業団地の中のもっと広い工房に引っ越し、そこも訪れました。
需要があるんですね…
—
文化の違う国で訪問先を訪ねるのは、時に困難を伴うこともあります。
オーストラリアのメルボルンから1時間半、Harcourt という小さな町にある
Morris Minor Garage
プライベートミュージアムを訪問した時のことを思い出します。
オーナーの連絡先は公開されていますが、所在地は非公開。
コンタクトを取ってから向かいました。
やはりパっとは探せず、行ったり来たり…
いくら走っても、景色がずーっと変わりません。
りんご農園とワイナリーだらけ。

そして見つけたのは、やっぱり『ゴミ箱』。
あーこんなんじゃ、わかんないって…

2エーカーのオリーブ畑、自宅、りんごの木もたくさん。
そんなところにプライベートミュージアムはありました。


この頃は、イギリスだけでなくオセアニアにも足を伸ばしていました。
ずいぶん時間が経ったなぁ。